働く人々
UI /UXに込められた「DMM TVらしさ」〜DMM史に残る!「DMM TV」&「DMMプレミアム」開発秘話〜
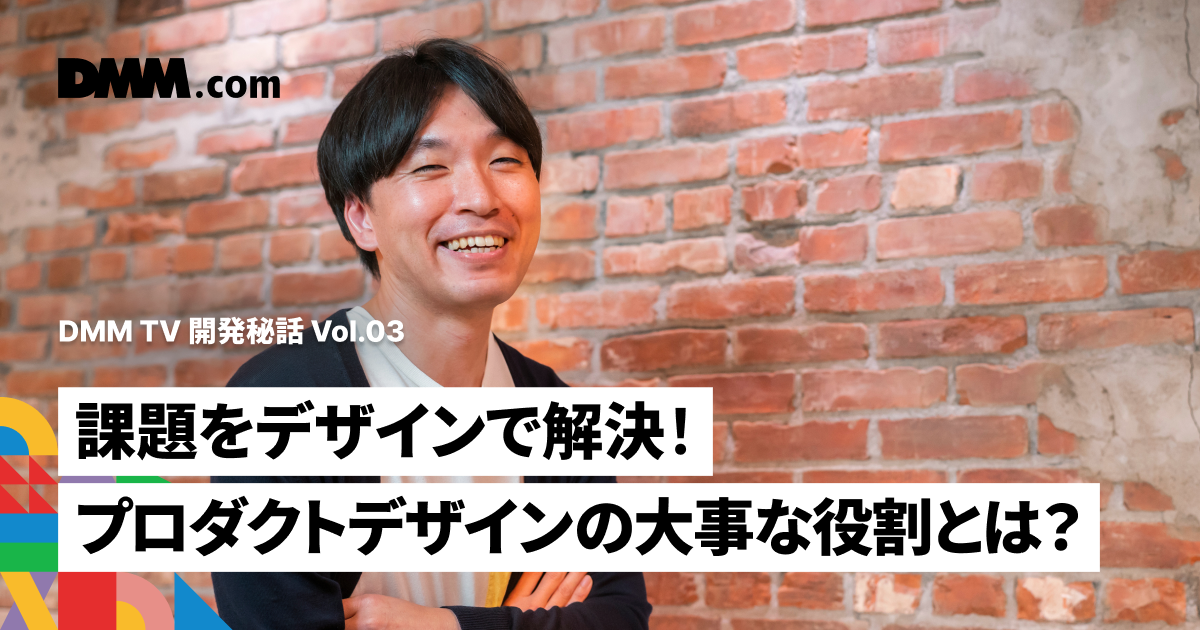
サービスの使いやすさを大きく左右するプロダクトデザイン。「DMM TV」の開発時にはインハウスのデザインチームが組成され、プロダクトデザインの設計において大きな力を発揮しました。デザインプログラムマネージャーとしてチームを率いてきた動画配信事業部の大塚に、当時の苦労や学び、DMMらしさを感じた出来事などについて聞きました。
- 大塚 潤デジタルコンテンツ本部 動画配信事業部 デバイスアプリグループ マネージャー







