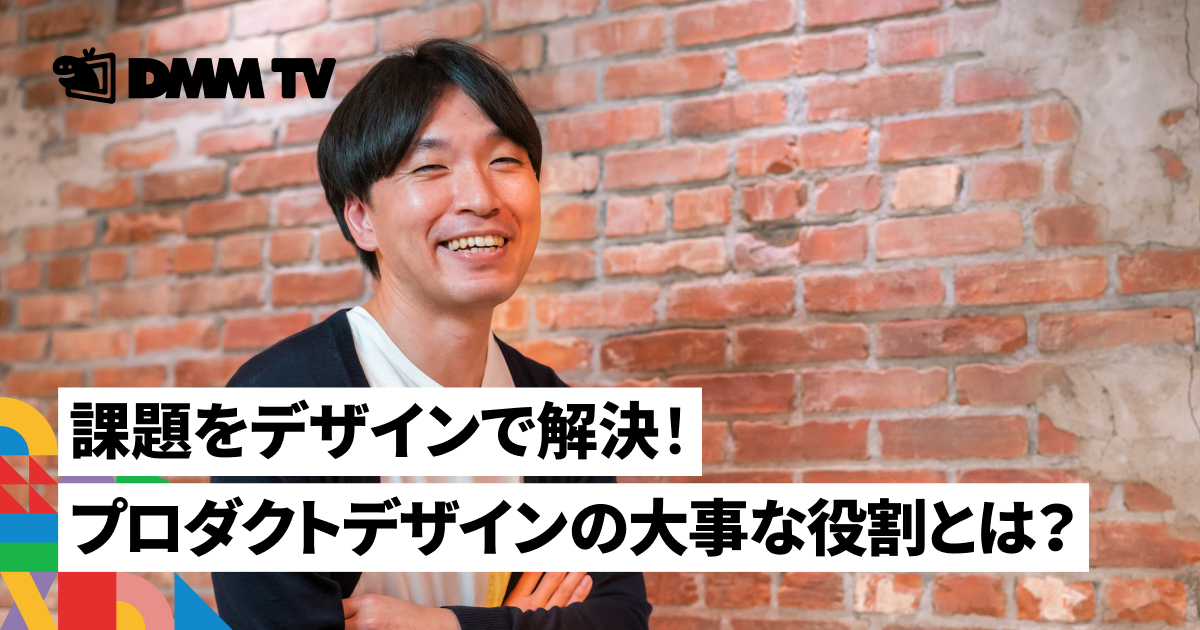働く人々
DMM史に残る!「DMM TV」&「DMMプレミアム」開発秘話〜SREとバックエンドエンジニア編〜

DMMが新たにリリースした「DMMプレミアム」と「DMM TV」。開発に携わった関係者に話を聞き、リリースまでの裏側を連載でお届けしています。今回は新技術にチャレンジし続けるSREとバックエンドエンジニアにフォーカスして、「DMM TV」の開発を支えた動画配信事業部の菅野と小林、テックリード室の山本に、それぞれどのようにしてこの大規模プロジェクトを乗り切ったのかを伺いました。
- 菅野 滉介デジタルコンテンツ本部 動画配信事業部 配信インフラグループ 配信インフラチーム
- 小林 辰彰デジタルコンテンツ本部 動画配信事業部 配信インフラグループ 配信インフラチーム
- 山本 将貴テックリード室 第1グループ