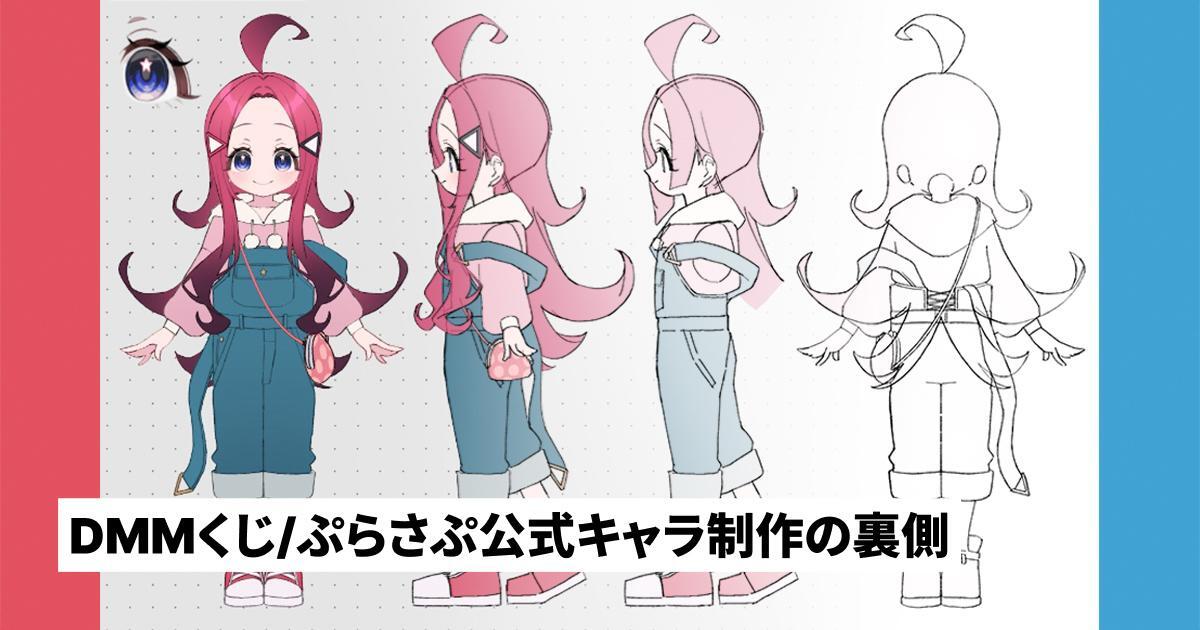働く人々
漫画実写化の常識を覆す!『夫を社会的に抹殺する5つの方法』ドラマ制作の裏側

2023年1月よりテレビ東京系にて放送されたドラマ『夫を社会的に抹殺する5つの方法』(以下『オトサツ』)が描くのは、夫婦の間で巻き起こる復讐劇だ。放送が開始されると、クズすぎる夫・大輔(演:野村周平)に妻・茜(演:馬場ふみか)が次々と復讐を遂げていくカタルシスが評判を呼び、全話100万回再生を突破。エピソード別の見逃し再生数では、テレビ東京の全番組の歴代トップ10に6本がランクインするヒットとなった(*)。 *配信開始から8日間の再生数(配信開始日を0日目として7日目まで) 本作の原作はDMMグループのデジタル漫画の制作スタジオGIGATOON Studioによるオリジナル作品で、2022年10月の配信開始からわずか1カ月あまりで実写ドラマ化が決定した。 一般に漫画原作ドラマといえば、ヒットした作品を実写化するのがセオリーだ。だが同作では、原作とドラマの制作がほとんど同時進行で進んでいく異例の手法がとられている。なぜそんなことが実現できたのか。制作の舞台裏をドラマ『オトサツ』プロデューサーのテレビ東京・倉地雄大氏、GIGATOON Studio COOであり本作の担当編集でもある五十嵐悠、DMM電子書籍事業部 プロモーショングループの野田昌嗣に聞いた。 ※2023年9月1日に、株式会社フューチャーコミックス、株式会社コミックストック、株式会社GIGATOON Studioの3社が統合され、株式会社CLLENNに変更されました。
- 野田 昌嗣(のだ まさし)電子書籍事業部 プロモーショングループ マネージャー
- 五十嵐 悠(いがらし はるき)二次元事業本部GS事業部 コンテンツ企画グループマネージャー
- 倉地 雄大さんテレビ東京/ドラマ「夫を社会的に抹殺する5つの方法」プロデューサー