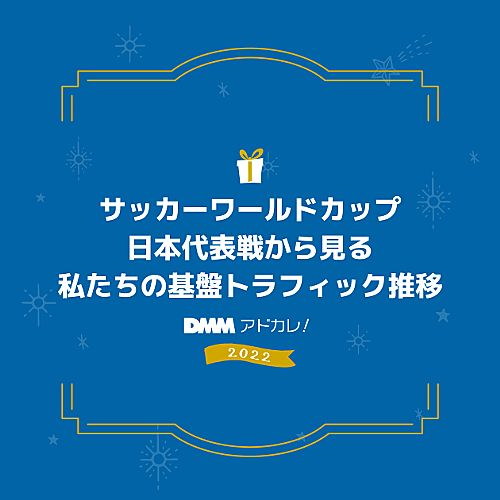働く人々
世界トップクラスの動画配信技術編〜DMM史に残る!「DMM TV」&「DMMプレミアム」開発秘話〜

日々膨大な数の映像コンテンツを配信する「DMM TV」。ユーザーに最高のエンタメ体験を届けるため、映像や作品情報の品質にとことんこだわっています。その実現に向けて尽力したのが動画配信を支える配信基盤グループと業務ハックグループ。今回は4人のメンバーにDMM TVを支える配信技術の裏側とプロジェクトで直面した困難、そして特にこだわって実装したアニメ配信にかける想いを金沢事業所にて聞きました。
- 矢野 完人(やの まさひと)デジタルコンテンツ本部 動画配信事業部 配信基盤グループ マネージャー
- 中村 航(なかむら わたる)デジタルコンテンツ本部 動画配信事業部 配信基盤グループ
- 薜 伸彦(まさき のぶひこ)デジタルコンテンツ本部 動画配信事業部 配信基盤グループ
- 山口 良平(やまぐち りょうへい)デジタルコンテンツ本部 動画配信事業部 業務ハックグループ